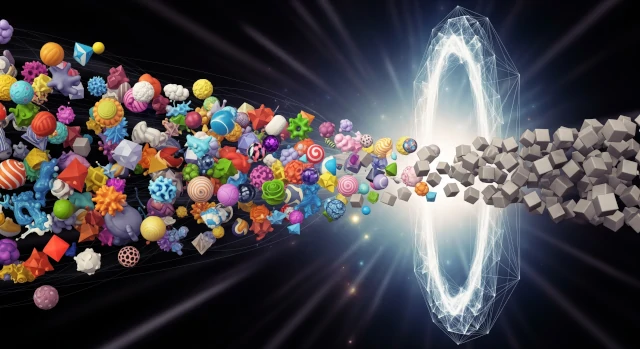
レガシーシステムのモダン化と「Fit to Standard」
レガシーシステムモダン化委員会の第4回議事要旨が公開されました。
公開からだいぶ日が経ってしまいましたが、溜まっている資料をガンガン読んでいきたいと思います。
レガシーシステムモダン化委員会
https://www.ipa.go.jp/disc/committee/legacy-system-modernization-comittee.html
レガシーシステムモダン化委員会は、その名の通り、「レガシーシステム」の「モダン化」について検討する委員会です。
少し用語を説明しましょう。
「レガシーシステム」というのは、端的に言うと「古いシステム」、過去の遺産です。
大抵は少しネガティブな意味も込めて、時代遅れのシステムというような意味合いを持ちます。
これに対して、「モダン化」というのは、時代にキャッチアップさせようという取り組みのことです。
日本語的には、「モダン」が死語っぽい気もしますが、元々英語から来ている用語なので、そこはぐっと飲み込んでおきましょう。
というわけで、この委員会の目的をザックリ説明すると、『時代遅れのシステムをどうやって今風にするか』ということになります。
では、実際にはどんな点が検討事項として挙がっているのか?
第4回の議事要旨によると、次のような点が議題にあがったようです。
- 経営者意識の弱さ
- 標準化、Fit to Standard に対する抵抗感
- 人材需給のギャップ
(第4回レガシーシステムモダン化委員会議事要旨)
https://www.ipa.go.jp/disc/committee/begoj90000002xuk-att/legacy-system-modernization-comittee-20250304-minutes.pdf
また、過去の議事要旨を参照すると、次のような点も憂慮されています。
- モダナイズに対するモチベーション不足
- モダン化後の再レガシー化
- DXに対する誤解
(第1回 レガシーシステムモダン化委員会 議事要旨)
https://www.ipa.go.jp/disc/committee/begoj90000002xuk-att/legacy-system-modernization-comittee-20240912-minutes.pdf
(第2回 レガシーシステムモダン化委員会 議事要旨)
https://www.ipa.go.jp/disc/committee/begoj90000002xuk-att/legacy-system-modernization-comittee-20241017-minutes.pdf
(第3回 レガシーシステムモダン化委員会 議事要旨)
https://www.ipa.go.jp/disc/committee/begoj90000002xuk-att/legacy-system-modernization-comittee-20241212-minutes.pdf
いずれにしても、課題が山積みであることは明らかです。
さすがに全部を語るスペースもないので、今日は『標準化、Fit to Standard に対する抵抗感』について考えてみようと思います。
これは先日、昔所属していた会社の先輩と帰りが一緒になったときのお話です。
システム開発という仕事について、方法論だとかこれまでの変遷などを、取り留めなく語り合っていました。
そんな中で、「Fit to Standard」のお話が出てきました。
「Fit to Standard」の概念は、『標準に合わせろ』という非常にシンプルなものです。
ただ、今の日本では、それが非常に重要な概念になっているといわれています。
どういうことでしょうか?
これまでの日本のシステム開発は、基本的に『業務に合わせたシステムを作る』という考え方で進められてきました。
大小様々な企業や自治体が、自社の業務に合うようなシステムを発注し、大手企業から地元企業まで、様々なベンダーがそれに従ってシステムを作ってきました。
ですが、DXなどが推進される現代では、その考え方が色々と邪魔になっているのです。
以前も記事で取り上げましたが、昨年の能登半島地震の際にも言われたように、各組織がシステムを持ち寄って情報交換をしようとしても、データの形式が違うから連携できない。
なんでそんな作りになっているかというと、各組織が自分たちに都合の良いようにシステムを作らせたから。
自社のシステムを作るときに、わざわざ緊急時を想定してデータ連携まで考えて作るケースは稀です。
国や省庁の決まりで仕方なく作りこむようなケースがほとんどでしょう。
一方、世界に目を向けると、日本のような考え方ばかりではありません。
特に欧州では、『標準に合わせて業務を変える』という考え方もそれなりに広まっています。
これがどういうことかというと、いざ他のシステムと連携をしようとしたときに、データをお互いにやりとりしたり、出力をつなぎ合わせることが容易だということです。
実際、欧州では「データスペース」という概念で、データの自由な流通を促進する枠組みがかなり進んでいます。
多少強引な言い方をすると、この「データスペース」を活用すれば、地震などの緊急時にも迅速にシステムの連携がとれるということです。
DXが進み、情報を『活用』することが意味を持つ今の時代において、このような特性は非常に重要です。
日本に話を戻します。
先に述べたように、今の日本には「Fit to Standard」の考え方が浸透していません。
せっかく「レガシーシステム」を作り変えられるタイミングだというのに、また『業務に合わせたシステム』を作ろうとしているのです。
そんなものを作っても、結局 Standard の流れに取り残され、再びレガシー化してしまうのは目に見えています。
DXが叫ばれて久しいですが、真にDXを行うならば、今このタイミングで「Fit to Standard」に切り替えるべきです。
つまり、既存の業務フローを見直し、標準に合わせられるところは合わせていく。
それは作業の手順かもしれませんし、データの形式かもしれません。
ですが、それを合わせておくことで、この先に待っている、情報を相互に『活用』する時代にも適合したシステム・業務に洗練されるはずです。
とはいえ、そう簡単にいかないことも理解しています。
一緒に帰った先輩との話でも、その点は議論になりました。
その際に特に問題となったのは2点。
ひとつは、「Fit to Standard」に直せるほどの予算も期間もないこと。
もうひとつが、自社の独自性を失うのではという恐怖です。
ひとつめの予算も(開発)期間もないというのは、中々難しいところです。
これは委員会でも指摘されていたように、経営層がどれだけの危機感をもって挑んでいるかという点も関わってきます。
また、Standard に fit していない部分が多すぎるというのも問題かもしれません。
そうなると、段階的に fit させていく戦略が必要となる可能性もあります。
ふたつめの独自性を失うのではないかという恐怖は、はっきり言って誤解です。
『パブリックなデータスペースなんてできたら、業務情報が筒抜けじゃないか』という話があります。
これは完全に誤解で、他社との競争に必要な重要情報は、当たり前ですがパブリックな空間で共有したりしません。
あるいは、先輩からは『なんでも標準に合わせてしまうと、独自色がなくなってしまうのでは』という懸念も提示されました。
これもやはり同様で、自社の独自色を出す部分、すなわち競争領域においては、Standard に合わせる必要などありません。
当然、そこは自社の独自性を出して勝負しにいくべきです。
ただ、勝負をするシステムでも、勝負をしなくていい部分、例えば、データをファイル出力する際の形式などは、Standard に合わせたほうがいい。
そういうお話です。
Fit to Standard のお話は、結局、従来の『業務に合わせたシステム』というのが、時代遅れになってしまったというお話です。
そして、これからは『システムに業務を合わせる』時代だと。
ただ、今までと180度方向転換するのは容易ではありません。
だからこそ、冒頭に挙げたような委員会まで立ち上げて、どうやって促していくかを国を挙げて考えていると。
そういうことなのでしょう。
今回は Fit to Standard のお話を取り上げましたが、デジタル庁では他にもたくさんのワーキンググループ(委員会)が活動しています。
国策などに興味がある方は、一度デジタル庁のホームページを覗いてみると、面白い発見があるかもしれません。
それでは、レガシーな考え方から脱却したい、山本慎一郎でした。
