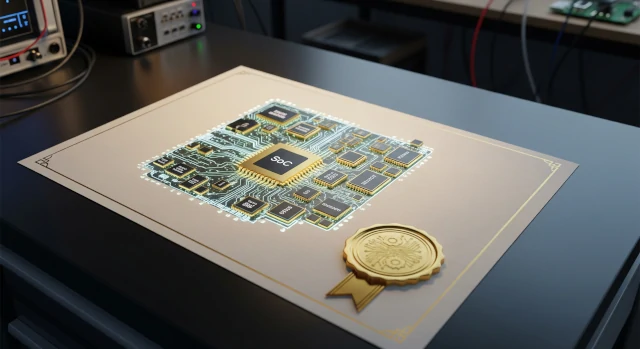
エンベデッドシステムスペシャリスト試験の結果
情報処理技術者試験の合格発表がありました。
エンベデッドシステムスペシャリスト、無事合格していました。
毎回受験するたびに思うのですが、合格発表は何度経験しても心臓に悪いです。
今まで、絶対に合格していると自信があったためしなんて1度もありません。
初めて受けたソフトウェア開発技術者が、受かってるだろうと高をくくっていてギリギリ合格だったため、いつも不安です。
さて、そんなエンベデッドシステムスペシャリスト。
公表された統計情報では、合格率は16%とのことで、まあ高度試験の平均かなという印象でした。
ただ、私が受験した福岡県の合格者は、私を含めて5人。
統計情報によると、実際の受験者は46人だったそうなので、11%程度の合格率です。
もしかして、合格者の地域分布の偏りが強いのかと思い、統計情報を確認してみたところ、全305名の合格者のうち、首都圏で150人程度、関西圏で50人程度と、かなり集中しているようでした。
合格者0人の県も多数あり、『一部の技術力のある企業で仕事に携わっている人しか合格できなかった』というような状況もあるのかもしれません。(個人の推測です)
もっとも、それよりも特筆すべきは『合格者の平均年齢』です。
昨年度までのエンベデッドシステムスペシャリスト試験では、おおよそ33~34歳で推移していたのですが、今年はなんと37歳。
ちょうど、例年のエンベデッドシステムスペシャリストとITストラテジストを足して2で割ったような年齢です。
来年度以降がどうなるかですが、少なくともシステムアーキテクト級の難易度になるのではないかと思います。(個人の感想です)
ところで、気になる(?)私の成績ですが、午前Ⅱが92点、午後Ⅰが78点、午後ⅡはA評価でした。
午前Ⅱはまあ、マークシートなので。
長年受験している経験値が違いますし、前回合格したときも96点でしたので、妥当と言えば妥当ですね。
午後Ⅰは、思ったより高得点だな、という印象です。
正直、時間が無くなってとりあえず埋めた欄もいくつかあったことを考えると、自信をもって回答した設問はほぼ完璧だったようです。
通過していても、60点スレスレだと思っていたので、このへんはもう少し自信を持ってもよいのかもしれません。
で、午後Ⅱが小論文です。
こちらは得点は出ずに、評価としてA~Dで判定、A評価なら合格という基準です。
なので、細かい事は分かりません。
ただ、それだけでは何の参考にもならない記事なので、午後Ⅱで何を書いたか公開しておこうと思います。
(実際の問題冊子のメモなどは、資料ページで公開しています。ご参考ください)
まず、回答した設問は、問1です。
『組込みシステムの製品企画段階における脅威分析について』というテーマでした。
問題の内容については、IPAの過去問題を参照していただきたいと思いますが、大筋としては、『脅威をどのような視点で分析して、どのような対策をとったか』、というような問題でした。
ご推察の通り、ストラテジ寄りの問題です。
で、私が書いた内容は、『AR合成配信設備機器の市場競争、及び、材料調達の競合』についてです。
初めに断っておきますが、私がそのような仕事をしていたという意味ではないです。
私の経験を元に、そのような状況下に置かれたら、こういうことを考えこういう対策を行います、ということを論述したものです。
それで肝心の内容ですが、コロナ禍で集合型イベントができなくなった層、つまり、演劇やライブ運営会社を顧客とする、映像機材の企業を想定しました。
元々、その会社ではライブの撮影機材などを取り扱っていたものの、コロナ禍によって業績が低迷、その打開策としてAR技術に進出したというシナリオです。
設問の核心はここからですが、じゃあその事業を始めるに当たってどのような脅威があるか。
まずはその洗い出しと分析から始めなければなりません。
そこで私が持ち出したのが、「PEST分析」と「過去の経験」です。
「PEST分析」というのは、対象をとりまく「Politics(政治)」、「Economy(経済)」、「Society(社会)」、「Technology(技術)」の観点から影響を分析する、経営などの手法です。
必ずしも脅威分析に使うものではありませんが、本問の状況から考えて、それらの観点から分析するのは有効だと考えられました。
特に、近年では海外製の安価で高品質な機材も増えてますし、材料調達の地政学的なリスクも増大しています。
そう考えると、国産であることがデメリットとなる可能性もあります。
そういった影響力を分析するうえでも、どの国が脅威となるかなどを「PEST分析」で検討することは意義のあることです。
一方、「過去の経験」というのも非常に強力な武器です。
本問では、『仮想通貨のマイニングが流行した際にも、材料調達が厳しくなった経験がある』という経験を持ち出しています。
題材として取り上げたAR技術の合成配信では、リアルタイムで画像処理を行うため、非常にパワフルなグラフィック処理回路が必要となります。
現に、テレワークなどの普及や生成AIの流行により、グラフィック処理回路を搭載したパーツ(グラフィックボード)は品薄になっていますので、状況と経験としてはベストマッチです。
また、ストラテジストとして様々な技法を知ると、ついつい『名前のついている技法』にとらわれがちになります。
そんな中で、「過去の経験」という古典的な方法も、非常に有効な手段として活用していますよ、というアピールをする狙いもありました。
最終的に、小論文の結論としては、そのような分析や経験から得られた情報を元に、他社や海外の状況を常にをチェックする、部品調達に複数のチャンネルを用意する、さらに、競争に勝つためにハード部門とソフト部門で協調するなどの対策を論述しました。
午後Ⅱの問題では、稀に結論である設問ウが捻った内容になることもあるのですが、今回はオーソドックスだったため、そのまま結論までいけました。
そんな感じで、論述しきったのが、たしか試験終了10分前ぐらいだったと思います。
意外と余裕がある?
いえいえ、そんなことはありません。
このあと、論文の前にある『論述の対象とする製品又はシステムの概要』を記入しなければなりません。
むしろギリギリです。
『論述の対象とする製品又はシステムの概要』は、システムの名前や開発工数、メンバーの人数、予算規模などを書く欄です。
かつては、『記入されていない場合、減点されることがある』程度の注意書きでしたが、記憶が確かなら、今回は『記載内容に矛盾がある場合、減点されます』と明確に断言されていました。
ですので、ここもしっかりと書かないと、いくら素晴らしい論文でも不合格になってしまう可能性があるわけです。
時間がなかったので、何をどう書いたのかメモれてませんが、予算をちょっと多めにしたのは覚えています。
論述でも述べた材料調達の競合などで、原材料高騰の可能性なども考慮し、さらに短期間で一気に製品化するスケジュール感にしたため、多少費用が膨れたイメージです。
このへんは、『実際に自分がその状況化におかれたとしたら、周りはどんな状況か? 何を求められるか? 何を取って何を捨てるのか?』などをしっかりと考えて、現実的なシミュレーションを行うことで導かれます。
そうして全部書き終わったのが、確か試験終了の1、2分前です。
うーん、ギリギリ。
論述内容の見直しなんてできません。
解答用紙に試験番号を書いたか、回答する問題番号を丸で囲んだかなど、最低限の確認だけして、後は天に任せます。
余談ですが、午後Ⅱ試験などでは、試験開始から一定の時間が経過すると退出が可能になるのですが、今回の試験ではかなりの人数がドロップアウトしていきました。
私の会場は40人程度だったと思うのですが、15人近く席を立たれたように感じました。
毎回、数名のドロップアウトはいらっしゃいますが、さすがに10人以上は初めて見ました。
それほど、従来の試験とは勝手が違ったということなのでしょう。
というわけで、新制度エンベデッドシステムスペシャリスト試験は、無事合格で幕を閉じました。
もうここ数日、合格発表のことが頭から離れなくて、ずっといや~な気持ちになってました。
春にネットワークスペシャリスト試験でポカしていただけに、余計に悲観的になっていたのかもしれません。
ともあれ、これでひと区切り……あれ?
考えてみれば『秋期試験不敗神話』は継続ですね。
- ソフトウェア開発技術者(2008年)
- ネットワークスペシャリスト(2010年)
- システムアーキテクト(2011年)
- ITサービスマネージャ(2012年)
- ITストラテジスト(2013年)
- 情報セキュリティスペシャリスト(2014年)
- システム監査技術者(2022年)
- エンベデッドシステムスペシャリスト(2023年)
勉強の秋ということで相性がよいのでしょうか?
逆に言うと、次は相性の悪い春期試験。
ネットワークスペシャリストにリベンジ……でしょうか?
まだ悩み中です。
それでは、これで安眠できると胸をなでおろした、山本慎一郎でした。
